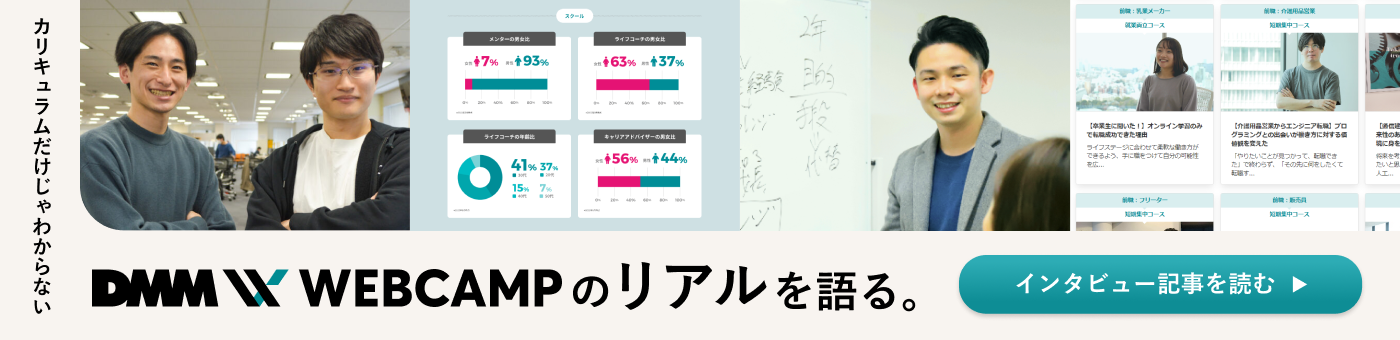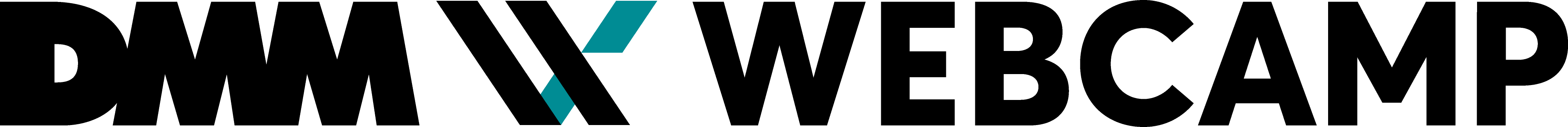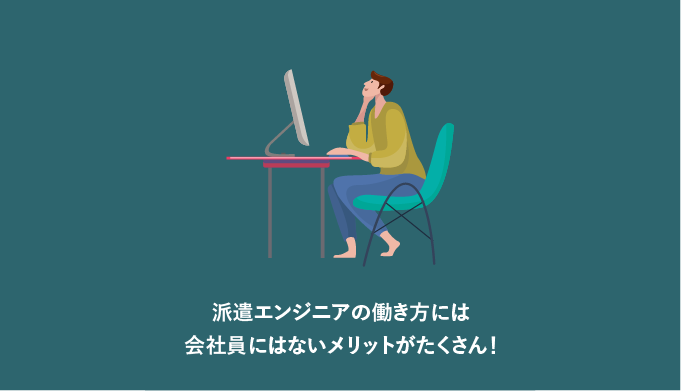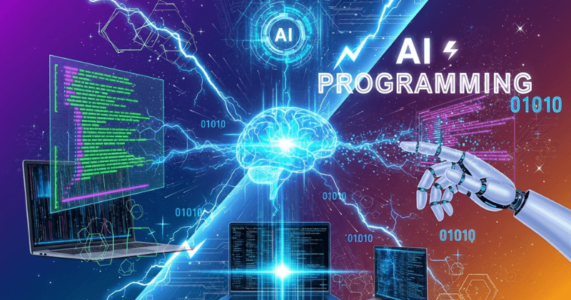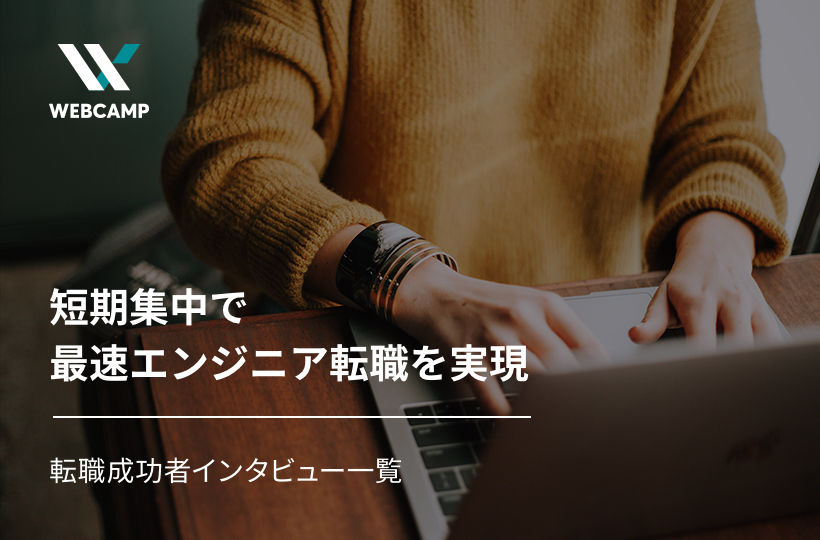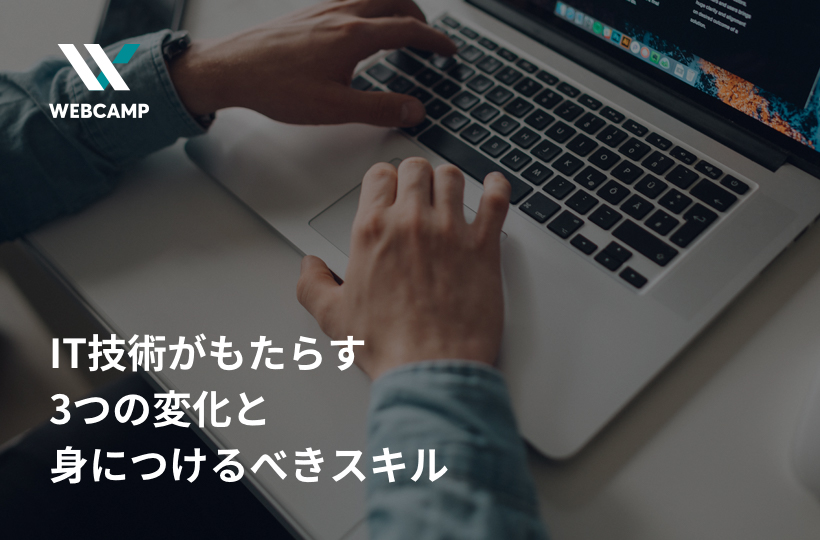エンジニアにおすすめの大学や専門学校はココ!実績ある学校や選び方を解説
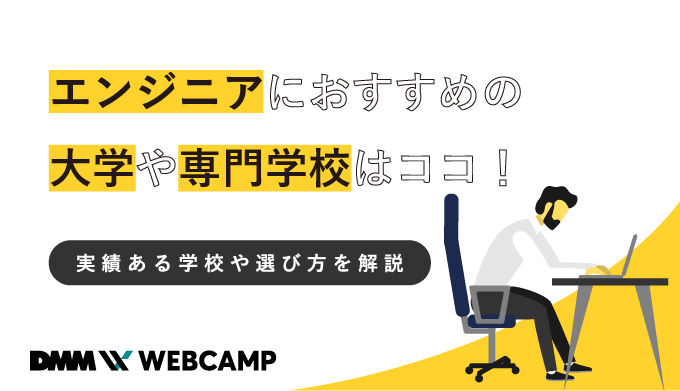
「エンジニアにおすすめの学校はどこ?」
「大学と専門学校ならどちらにいくのがおすすめ?」
と思うことはありませんか?
エンジニアになろうとしても、進路がいろいろあって迷ってしまいますよね。
では、エンジニアになるための進路はどのようなものがあるのでしょうか?
そこで今回は、
- エンジニアになるための進学の方法
- 大学や専門学校のそれぞれのメリット・デメリット
- エンジニアにおすすめの大学や専門学校
について詳しく解説します。
この記事を見ればエンジニアになるための進学方法について必ず理解できます。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
そもそもエンジニアにはどんな仕事がある?7つの種類を解説
エンジニアになるといっても実はたくさんの種類があります。
なりたいエンジニアの種類によって、学ぶべき項目などが違ってきます。
まずはエンジニアの種類について確認しましょう。
- システムエンジニア(SE)
- プログラマー
- Webエンジニア
- データベースエンジニア
- ネットワークエンジニア
- セールスエンジニア
- データサイエンティスト
エンジニアの種類はおもに上記の7つがあります。
それでは1つずつ紹介していきます。
また、もし未経験からエンジニアを目指す際には下記記事も参考になるので、あわせてご確認ください。
1.システムエンジニア(SE)
システムエンジニア(SE)は顧客からの要望により、システム全体の設計をおこない最適なシステム開発をする仕事です。
システムエンジニア(SE)の仕事は上流工程である設計書を作成するだけではなく、システムを管理するプロジェクトチームや予算なども管理します。
おもに上流工程の「要件分析」「要件定義」「基本設計」「詳細設計」などを担当することが多い職種です。
2.プログラマー
プログラマーはシステムエンジニア(SE)が作成した設計書に基づいてプログラミング作業をおこなうのが主な仕事です。
設計に基づいてプログラミングするだけではなく、完成後も仕様バグのチェックや改善をするのが大きな役割となります。
プログラミング言語はたくさんの種類があるので、それぞれ得意なジャンルのプログラマーがいるのも特徴のひとつです。
3.Webエンジニア
Webエンジニアはわたし達が日常でよく使うWebサイトやECサイトのWebサービスに必要なシステムの設計や開発をおこなっています。
Webサイトの構築のためのプログラミングだけではなく、セキュリティやネットワークの通信に関わる知識なども要求されるでしょう。
Webエンジニアは利用者がよくみる画面を構築する「フロントエンジニア」とサーバーやOSなどのシステム開発をする「バックエンドエンジニア」の2つにわかれています。
4.データベースエンジニア
データベースエンジニアはデータベースの設計・構築・保守・運用などをおこなうエンジニアの総称です。
企業の顧客データなど膨大な情報をデータベースに保管し管理するためとても責任のある仕事です。
データベースエンジニアは企業のデータベースのシステムの開発や運用をまかされ、その膨大なデータをビジネスに活かせるように最適化するのが大きな役割となります。
5.ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアは企業のネットワーク構築をおこなうエンジニアです。
企業のパソコンどうしをつなぐネットワークを構築するためにプログラミングをしたり、実際にパソコンやモデムやルーターなどの周辺機器をつないだりする役割があります。
最近では、社内のネットワークのみならずクラウドサーバーを利用することが多いため、セキュリティに関する知識が必要となっています。
6.セールスエンジニア
セールスエンジニアはプログラミングと営業を両方するエンジニアのことを指します。
商品をセールスするときに、システム開発ができるエンジニアが説明したほうが説得力が高く、顧客が安心して相談できます。
アフターフォローのときも、セールスエンジニアが顧客を訪問することでトラブルなどが発生したときにも迅速に対応ができるため貴重な存在となります。
7.データサイエンティスト
データサイエンティストは企業が集めた膨大なビッグデータの分析をして、それをビジネスに応用できるようにするのが主な役割です。
とくにWeb系のショッピングサイトやソーシャルゲームなどの企業では、膨大な顧客情報や商品データを集積します。
データサイエンティストは数学や統計学などの知識が必要となります。
データサイエンティストは解析したデータをもとに企業にビジネスのアドバイスなどをおこなうのです。
エンジニアにも上記のようにいろいろな種類があるので、自分に合った職種を選ぶのも大切ですね。
8.インフラエンジニア
インフラエンジニアは、情報システムの基盤となるインフラストラクチャーを構築・運用する専門家です。
具体的な業務内容はサーバー・ネットワークの構築、クラウド環境の管理、セキュリティ対策、バックアップ・復旧策の実施などで、システム全体の安定性やセキュリティを確保するために重要な役割を果たしています。
運用の効率化や新技術の導入、トラブル対応なども担当し、常にシステムの最適化に取り組んでいます。
エンジニアの中でも特に基盤を支える役割を担うため、柔軟性と専門知識が求められます。
9.セキュリティエンジニア
セキュリティエンジニアは情報システムやデータの保護を担当する専門家です。
セキュリティポリシーの策定、セキュリティシステムの設計・構築、脆弱性診断・対策、セキュリティインシデントへの対応などが主な業務です。
情報漏洩やシステムへの不正アクセスなどのリスクを最小限に抑えるために、常に最新のセキュリティ技術や脅威に関する知識を身につける必要があります。
また、セキュリティポリシーの遵守や教育活動も行い、組織全体のセキュリティ意識向上にも取り組んでいます。
セキュリティエンジニアは、情報セキュリティがますます重要となる現代社会において不可欠な存在となっています。
10.アプリケーションエンジニア
アプリケーションエンジニアは、ソフトウェア開発においてアプリケーション(ソフトウェア)を設計・開発する専門家です。
主にユーザーが利用するアプリケーションの機能やインターフェースの設計、プログラミング、テスト、および維持管理を行います。
ユーザーのニーズや要件を理解し、それを基にシステムやアプリケーションの設計を行ったり、プログラミング言語やフレームワークを用いたりしてアプリケーションを実装し、テストを行って品質を確保します。
アプリケーションエンジニアは、ソフトウェア開発のプロセス全体に関わることが多く、チームで協力してプロジェクトを進める能力も求められます。
「なんか今の仕事合わないな・・・」
「IT業界に転職してみたいなぁ・・・」
という方、DMMが運営する「WEBCAMP エンジニア転職」をご検討してみてはいかがですか?

「WEBCAMP エンジニア転職」では最短12週間でITエンジニアを目指すことが可能です!
WEBCAMPの卒業生は転職後に年収もUP!(例:年収250万円→500万円)
しかも今なら受講料の最大70%が給付金として支給されます。
DMM WEBCAMPは経済産業省・厚生労働省が認定した専門実践教育訓練給付金制度の対象です
大学は必須ではない?学生がエンジニアになるための3つの方法
エンジニアになるためには資格や学歴はとくに関係ありません。
大学で情報工学や電気工学などの基礎知識を学んでおくことは就職のときに多少有利です。
IT業界は現場に出てからが勝負なのでそれほど気にする必要はありません。
学生がこれからエンジニアになるためには、おもに以下の3つの方法があります。
- 大学を卒業する
- 専門学校を卒業する
- 高卒ですぐに就職する
もちろんエンジニアには異業種からの転職も可能ですが、学生から最短ルートで転職する場合は、上記の方法で問題ありません。
それぞれに特徴があるので以下で詳しく説明します。
1.大学を卒業してエンジニアになる
大学で情報処理や情報工学そして電気工学などを専攻して卒業するとエンジニアになりやすいです。
理系の大学卒業者が多いですが、企業の教育体制も整っているため、文系卒業者でもエンジニアになることは可能です。
大学では一般的な教養や科目も学習するので、卒業後にエンジニア以外の幅広い分野に就職できるという特徴があります。
エンジニアとしての専門知識を学ぶ以外に、ほかのことを学んだり社会に適応できる総合力を身につけたりしたい人は大学に通うのがおすすめです。
2.専門学校を卒業してエンジニアになる
エンジニアになりたい人は専門学校に進学する人も多いです。
専門学校はエンジニアとして就職してからすぐに現場で活躍できるようにカリキュラムが組まれています。
そのため、エンジニアとしての専門的な知識や技術を短期間に習得できるのでとても人気があります。
やりたいことがすでに決まっている人には、専門学校に進学するのがおすすめです
3.高卒でエンジニアになる
金銭的な事情などで進学できない人でも、高卒でエンジニアになることが可能です。
IT業界は人手不足が続いているため、企業も積極的に採用しているところがあるからです。
高卒ですぐに現場に入ることになるため、実践の経験を早い段階で積めるでしょう。
エンジニアの仕事は現場で経験を積みながら覚えていくことが多いので、早くお金を稼ぎたい人は高卒からでも問題ありません。
ただ、知識が全くない状態でいきなり現場に出るのは不安だったり、経験不足だと就職先を選べなかったりします。
プログラミングスクールで開発実績を積んでおけば希望する就職先に行ける可能性がかなり高くなります!
DMM WEBCAMPではコースごとに「制作」を行い、開発経験を育みます!
確かな実力をつけて、「エンジニア就職」を実現させませんか?
エンジニアになるために大学に通うメリット
エンジニアになるために大学に通うとITに関する専門的な知識が深まります。
しかし大学ではITの知識を習得するだけでなく、社会に出てから役に立つことをたくさん経験できます。
大学に通うと以下のようなメリットがあります。
- 対人スキルが高められる
- 一般的な教養が身につく
- 就職活動のときに優遇されやすい
上記のような特徴があります。
それぞれについてさらに詳しく見ていきましょう。
1.対人スキルを高められる
大学に通うとたくさんの人と関わることが増えるため対人スキルが向上します。
大学にはさまざまな年代の人や違う学部などまったく価値観の違う人たちが集まっているのです。
大学生活が始まると幅広い交友関係が形成できます。
- サークルの先輩や後輩
- 大学ゼミの講師や教授
- アルバイト先の仲間
- 友達などを介したほかの大学生や社会人
このように大学の中だけでなく、すでに社会に出ている人たちや幅広い年代の人との関わりが増えてきます。
大学に通うことで自然にコミュニケーション能力が高まり対人スキルが身についてくるのです。
2.一般的な教養が身につく
大学に通うとIT系の専門知識のほかに一般教養を学べるので社会にでたあとに役に立ちます。
エンジニアになると幅広い年代や経験を積んだ人たちと一緒に仕事をする必要があります。
- 顧客との打ち合わせ
- ほかのエンジニアとの交流
- 職場内の人間関係
いくら専門的な知識が多くても現場の人(とくに上司や目上の人など)とうまく付き合っていかないと社会では通用しません。
そのため社会で生きていくためには基本的な一般常識や教養は必要です。
大学では一般的な教養を一緒に学ぶことができるのがメリットとなります。
3.就職活動の際に優遇されやすい
大学を卒業していると就職活動のときに優遇されやすいのが実情です。
エンジニアは実力社会の職業ですが、現代の日本においてはまだ学歴で判断されることが多いです。
1次試験や書類選考のときに同じくらいの能力だった場合、より高い学歴の人を採用する可能性が高いでしょう。
とくに大手企業はその傾向がつよく大卒の方が給料も高いため、エンジニアになるときは大学を卒業しているとメリットが大きくなります。
ただ、大学では実績を作るのが難しいのと実務ですぐに活かせるスキルが身に付きにくいという点もあるので、そこを補える部分があるといいですよね。
DMM WEBCAMではプロの現役エンジニアによる指導の下、確かなスキルが身につきます!
また、学習頻度も「週2回のマンツーレッスン」で大学と両立が可能!
まずは一度、無料体験をしてみてはいかがですか?
エンジニアになるために大学に通うデメリット
エンジニアになるために大学に通うのにはメリットもありますが、デメリットも少し存在します。
大学では4年間かけてさまざまな経験ができますが、その反面でエンジニアには関係のない学習があるからです。
大学に通うデメリットは以下の3つです。
- ITにあまり関係のない講義を受ける必要がある
- 専門学校よりも卒業に時間がかかる
- 専門学校に比べて学費が高い
この3点が大学に通うデメリットとなります。
それでは以下でひとつずつ見ていきましょう。
1.ITにあまり関係のない講義も受ける必要がある
エンジニアになるために大学に通うとIT以外の勉強をする必要があります。
エンジニアに関する勉強のほかに、ITとはまったく関係のない一般教養科目などを必修で受けなければ卒業できません。
ITに関する知識だけを学びたい人にとっては、ほかの授業は退屈になってしまう可能性があります。
大学に通うと興味のない科目まで勉強する必要があるので、時間を無駄に過ごしてしまう可能性があるのがデメリットとなります。
2.専門学校よりも卒業に時間がかかる
大学に通った場合は最短で4年かかるため、専門学校よりも2年ほど長く学校に通う必要があります。
エンジニアとして早く活躍したければ、この2年間は長く感じてしまうでしょう。
早く現場で実務経験を積めばエンジニアとしての技術力や知識が高くなります。
すぐにエンジニアとして活躍をしたい場合は、この2年の差がデメリットに感じる場合があります。
3.専門学校と比べて学費が高い
大学に通うと、専門学校を卒業するのに比べて学費が高くなってしまいます。
それは学校に通う期間が大学であれば4年、専門学校であれば2年と年数が違うからです。
卒業までにかかる費用(入学金も含む)を大学と専門学校で比較すると以下のようになります。
- 専門学校・・・316.9万円
- 国立大学・・・539.3万円
- 私立大学(文系)・・・730.8万円
- 市立大学(理系)・・・826.7万円
(出典:マイナビ進学)
このように専門学校と国立大学では200万円以上、私立大学にいたっては倍以上の費用がかかることがデメリットかかるがデメリットとなります。
エンジニアになるために専門学校に通うメリット
エンジニアになりたい人は専門学校に行くのが近道です。
専門学校に行くと就職に向けてのサポート体制が充実しているのでおすすめです。
エンジニアになるために専門学校に通うことのメリットはおもに3つあります。
- 短期間で実用的なスキルを習得できる
- 業界経験のある講師から指導を受けられる
- 資格取得のサポートをしてもらえる
これらのことが専門学校に通うメリットになります。
それではひとつずつ説明していきます。
1.短期間で実用的なスキルを習得できる
エンジニアになることを目標として専門学校に通うと、短期間で実用的なスキルを習得することができます。
生徒が卒業したあとに現場で即戦力となれるように、実践的な授業をおこなっているからです。
そして、エンジニアに関係のない科目の勉強をする必要がないので、エンジニアに関する知識を短期間で集中的に学べます。
専門学校にいくと短期間でスキルを身につけられるので、早くエンジニアになりたい人にはおすすめです。
2.業界経験のある講師から指導を受けられる
専門学校では業界の第一線で活躍した講師から直接指導を受けられるのがメリットです。
専門学校の講師は現場での体験をもとにより実践的で役に立つ指導をしてくれるため、実務の状況をリアルに感じられます。
IT業界のことにも精通しているため、業界の裏話など就職するときに参考になる情報をたくさんもっています。
専門学校はエンジニアとしての専門的な知識や技術のほかに、業界の内部情報などを教えてもらえるのがメリットです。
3.資格取得のサポートをしてもらえる
専門学校に通うと資格取得を目指すためのカリキュラムが組まれています。
資格を取得することによって、就職時に有利になるだけでなく実際に現場に行ったときの即戦力となれるからです。
例えば以下のような資格を取得できます。
- 基本情報技術者試験
- 応用情報技術者試験
- シスコシステムズなどのベンダー試験
ほかにもたくさんの資格がありますが、専門学校は取得のためのサポート体制がかなり充実しています。
これらの資格を持っていると就職時やキャリアアップの際に役にたちます。
専門学校に通うことで効率よく資格を取得できるのは大きなメリットです。
エンジニアになるために専門学校に通うデメリット
エンジニアになるために専門学校に通うとデメリットが2つあります。
専門学校に行くなら、将来のことをしっかりと考えてから進学を決めましょう。
入学してから変更ができないので、大学に行くのか専門学校にするのかをはっきり決める必要があります。
専門学校に通うデメリットは以下のふたつです。
- IT業界以外への進路変更が難しい
- 学歴を重視する企業には採用されにくい
以下で詳しく説明します。
1.IT業界以外への進路変更が難しい
エンジニアを目標として専門学校に進学したときは、IT以外の業界に進路変更するのが難しくなります。
専門学校なのでIT関係の専門的な勉強を中心におこない、それ以外の学習はしないからです。
そのため急にほかの業種に転職したいと考えても不利になってしまいます。
- 専門学校に行ったがIT系は向いていなかった。
- ほかの業界に興味がでてしまった。
- なんとなく専門学校に入学してしまった。
このようなことも十分に考えられます。
エンジニアになることを目標に頑張っていく覚悟がなければ、あとから苦労することになってしまいます。
専門学校はほかの業界に進路変更しにくいので注意が必要です。
2.学歴を重視する企業には採用されにくい
専門学校卒の人は学歴を重視する企業には採用されにくいです。
とくに大手の企業は学歴を重視する傾向があります。
大手企業はたくさん応募が集まるため書類選考の際に学歴をひとつの基準として見ています。
- 募集要項に大卒以上と書かれている
- 初任給が大卒よりも安くなっている
このように募集要項だけみても学歴を重視していることがうかがえます。
とはいえ、IT業界は実力主義の社会なので就職してからいくらでも挽回できます。
専門学校は就職するときに少し不利になることも頭にいれておきましょう。
どちらがいい?エンジニア志望におすすめな大学や専門学校の選び方
(出典:ステップアップエンジニア)
エンジニアになるために、大学か専門学校、どちらに進学すればいいのか迷いがちです。
ですが、実際のところ大学と専門学校のどちらがいいのかは一概にいえないため、自分の軸に合わせて進路を選ぶのがよいでしょう。
たとえば、ステップアップエンジニアでは、これからの進路を考える学生に向けて上記の表をまとめています。
このような形で、ご自身の希望に近いのはどちらかを吟味してみると、自分が目指すべき進路が明確になるでしょう。
他にも、選び方は以下のようなものがあります。
学べる知識の幅広さで選ぶ
幅広い知識を学ぶことで、将来のキャリアの選択肢が広がります。
選ぶ際には、カリキュラムやカリキュラム外の学習支援(インターンシップや研究会など)が充実しているかをチェックしましょう。
また、産業界との連携や実務経験の機会があるかも重要です。
業界に求められるスキルや知識を網羅的に学べる学校を選ぶことで、エンジニアとしての基礎をしっかりと身につけることができます。
エンジニアになるまでの期間で選ぶ
エンジニアになるまでの期間で学ぶ内容や進路が変わってくることがあります。
短期間で基礎を学びたい場合は、短期集中型の専門学校やオンラインコースが適しています。
一方、大学ではより幅広い知識や理論を学び、長期的なキャリアを見据えることができます。
また学ぶ期間が短くても就職や転職を目指す場合は、実務経験や就職支援などを重視した学校を選ぶと良いでしょう。
このように、学びたい内容や将来のキャリアを考慮しながら、自分に合った学校を選ぶことが重要です。
進路や目的に合わせて選ぶ
エンジニアになるまでの期間で大学や専門学校を選ぶのは重要ですが、それだけではなく進路や目的にも合わせて選ぶことが大切です。
例えば、大学では理論的な知識や基礎的なスキルを幅広く学ぶことができますが、専門学校では実践的な技術を重視した教育が受けられることもあるでしょう。
進路や目的に合わせて適した教育機関を選ぶことで、将来のキャリアに役立つ知識やスキルを身につけることができます。
エンジニアを目指せるおすすめの大学3選
エンジニアを目指して大学に進学する場合に、どこの大学がおすすめなのか気になる方も多いでしょう。
この章では、おすすめの大学を紹介します。
1.東京情報大学
東京情報大学は千葉県千葉市にある私立の大学で、エンジニアを目指す人は総合情報学部に進学するとよいでしょう。
総合情報学部は3つの学系統に体制が構築されていて以下のようになっています。
- 情報システム学系・・・システム開発、ネットワーク、AI
- 数理情報学系・・・数理情報、データサイエンス
- 社会成情報学系・・・メディアデザイン、経営イノベーション、人間情報
(出典:東京情報大学公式サイト)
東京情報大学は情報社会の仕組みを基礎から理解し実践力を身につけることに力を入れています。
それに加えてグローバルな社会にできるように語学や国際的なコミュニケーションを学べるのが特徴です。
2.東京電機大学
東京電機大学は東京都足立区にある私立大学です。
エンジニアを目指すためにさまざまなカリキュラムが組まれています。
課題解決型学習をとりいれているので自分自身の専門的な知識や技能を活用できるような人材を育てています。
- システムデザイン工学部
- 未来科学部
- 工学部
- 工学部第二部
- 理工学部
- 情報環境学部
(出典:東京電機大学公式サイト)
上記のような複数の学部があり、さまざまなジャンルのエンジニアに対応できます。
グローバルな社会に対応できるよう語学に力を入れています。
3.工学院大学
工学院大学は東京都新宿にある私立大学です。
工学院大学はアクティブラーニングを積極的にとりいれており、学生同士で議論をしたり自ら体験したりすることで学習理解度を高めています。
工学院大学の学部は以下の4つから構成されています。
- 先進工学部
- 工学部
- 建築学部
- 情報学部
(出典:工学院大学公式サイト)
エンジニアを目指すためには工学部や情報学部がおすすめの学部となります。
国際交流にも力を入れているので留学プログラムなども用意されているのが特徴です。
4.千葉工業大学
千葉工業大学は、工学部や情報科学部などの工学系学部が充実しており、エンジニアを目指す学生にとって理想的な環境を提供しています。
とくに情報通信システム工学科では、最新の技術や知識を学ぶことができます。
また、学内には充実した研究施設や実験設備が整っており、実践的な学びを重視しています。
さらに産学連携やインターンシップなどのプログラムも充実しており、学生が実際の業務に携わる機会も多く用意されています。
5.愛知工科大学
愛知工科大学は、工学部や情報科学部などの工学系学部が充実しており、エンジニアを目指す学生にとって理想的です。
特に情報メディア学科では、最新の技術や知識を学ぶことができる情報処理学科や情報ネットワーク学科などのコースがあります。
また学内には充実した研究施設や実験設備が整っており、実践的な学びを重視しているうえ、産学連携やインターンシップなどのプログラムも充実しており、学生が実際の業務に携わる機会も多く用意されています。
6.京都大学
京都大学は理工学部や情報学研究科など、エンジニアリング教育においても優れた環境となっています。
特に情報学研究科は情報科学を学ぶ上で非常に優れた環境が整っており、コンピュータサイエンスや人工知能、情報通信工学などの専門分野において高度な教育・研究を展開しています。
また京都大学は産学連携にも力を入れており、企業との共同研究やインターンシップなど、実践的な学びを提供する取り組みも積極的に行われています。
7.大阪大学
大阪大学も理学部や工学部など、エンジニアに必要な幅広い学問領域をカバーしています。
特にシステム科学科はエンジニアリング教育において高い評価を受けており、電気電子工学科や情報科学科などの学科では、コンピュータサイエンスや情報工学、電子工学などの分野において優れた教育・研究が行われています。
また、大阪大学は産学連携にも積極的に取り組んでおり、企業との協力関係を活かした研究や実務経験の積み重ねを通じて、学生が実践的なスキルを身につける機会を提供しています。
8.名古屋大学
名古屋大学は工学部や情報学研究科などを通じて、エンジニアリング教育に力を入れています。
とくに情報学研究科ではコンピュータサイエンスや情報工学、人工知能などの分野において、先端的な研究が行われています。
また名古屋大学は産学連携にも積極的に取り組んでおり、地域の企業や研究機関と連携したプロジェクトを通じて、学生が実践的なスキルを身につける機会を提供しています。
9.東京工業大学
東京工業大学(東工大)は、工学を中心とした理系教育に力を入れている大学で、特にエンジニアリングデザイン(ESDコース)はエンジニアリングの分野で優れた教育・研究を行っています。
東工大のエンジニアリング教育は、理論と実務を両立させたカリキュラムが特徴であり、実際の課題解決能力を身につけることができます。
また東工大は産学連携にも力を入れており、多くの企業と連携したプロジェクトを通じて、実践的な技術や知識を身につける機会を提供しています。
国際的な研究交流も盛んであり、世界各国の研究者との交流を通じて、グローバルな視野を持つエンジニアを育成しています。
10.九州大学
九州大学は九州地域を代表する国立大学であり、工学部もその中でも優れた教育・研究を行っています。
エンジニアリングの分野では、産官学連携や地域貢献活動を通じて、実践的な技術力を身につけることができます。
また工学部では幅広い工学分野を学ぶことができるため、将来的に「どのようなエンジニアとして活躍したいか」に応じて適した専門分野を選択することができます。
そのため九州大学でのエンジニアリング教育は、将来的にエンジニアとして活躍するための基盤を築けるでしょう。
11.北海道大学
北海道地域を代表する大学であり、工学部もその中でも高い評価を受けています。
エンジニアリングの分野では、幅広い工学知識や技術を学ぶことができるだけでなく、地域の産業や社会課題に対する解決策を提案する力も身につけることができます。
北海道大学の工学部では、理論と実務を組み合わせたカリキュラムを提供し、実践的なスキルを磨くことができるため、将来的にエンジニアとして活躍するための基盤を築くことができるでしょう。
12.東北大学
東北大学の情報工学コースも、エンジニアを目指せる大学として高い評価を受けています。
理論と実務を組み合わせたカリキュラムを提供し、実践的なスキルを磨くことができるため、将来的にエンジニアとして活躍するための基盤を固められるでしょう。
幅広い工学知識や技術を学ぶことができるだけでなく、地域の産業や社会課題に対する解決策を提案する力も身につけることができます。
将来的にエンジニアとして活躍するための準備としては最適でしょう。
13.筑波大学
筑波大学は大学として高い教育水準と研究力を持ち、特に工学システム学類はその中でも評価が高いです。
充実したカリキュラムと研究環境が魅力で、幅広い工学分野を学ぶことができるため、将来のキャリアの選択肢が広がります。
また、筑波大学は産学連携にも力を入れており、産業界との連携を通じて実践的な技術や知識を身につける機会が豊富です。
ちなみに、天才プログラマーと呼ばれる「登 大遊」氏も筑波大学の出身として知られています。
14.慶應義塾大学
慶應義塾大学は、エンジニア志望の学生にとって非常に魅力的な大学の一つといえるでしょう。
中でも特に情報工学部は高い評価を受けており、先進的な工学分野を学ぶことができます。
慶應義塾大学は産学連携が盛んであり、実践的な技術や知識を身につけるための様々な取り組みが行われています。
また国内外から優秀な学生が集まるため、刺激的な学習環境が整っているので、エンジニアを目指す方にも最適です。
15.早稲田大学
早稲田大学は、エンジニア志望の学生にとって魅力的な大学の一つです。
とくに先進的な工学分野を学ぶことができる「基幹理工学部情報理工学科」は、学内外での産学連携が盛んであり、実践的な技術や知識を身につける機会が豊富です。
また、優秀な学生が集まることで刺激的な学習環境が提供されており、自身の成長にも繋がります。
さらにエンジニア以外にも、幅広いキャリアパスを選択できる就職支援も充実しています。
16.東京理科大学
東京理科大学は、理工学を中心とした幅広い学問領域をカバーする大学で、エンジニア志望の学生にとって優れた環境を提供しています。
特に情報工学部や情報理工学部では実践的な教育が重視されており、産業界で即戦力として活躍できる技術や知識を身につけることができるでしょう。
また学内には様々な研究施設があり、最先端の技術や研究に触れる機会も豊富です。
17.神戸大学
神戸大学もエンジニア志望の学生にとって魅力的な大学の一つです。
工学部や理学部など、幅広い学部・学科があり、たとえば機械工学部では機械・電気・情報などの工学分野を学ぶことができます。
学内には先端技術を研究する施設も多く、最新の技術や知識を身につけることができます。
卒業後は、大手企業から研究機関まで幅広いキャリアパスがあります。
18.大阪府立大学
大阪府立大学は、エンジニア志望の学生にとって魅力的な大学の一つです。
特に工学研究科では、コンピュータやネットワークなどの情報技術を幅広く学ぶことができます。
また工学部の電気電子工学科や機械工学科も充実しており、最新の技術や知識を学ぶことが可能です。
大学独自の取り組みとしては、産学連携や地域との連携が盛んであり、実践的な学びや研究を行う機会が豊富です。
19.横浜国立大学
横浜国立大学は、エンジニアリング教育において高い評価を受けている大学の一つです。
情報技術やコンピュータ科学に関する幅広いコースを提供しており、学生は実践的なプロジェクトや研究活動を通じて技術力を磨けるほか、産業界や学術界でのキャリアを築く準備ができます。
また、横浜の立地条件を生かした産学連携プロジェクトも盛んであり、学生は実践的な経験を積むことができます。
20.埼玉大学
埼玉大学は、エンジニアリングに関連する学部や学科を有する大学です。
工学部では、機械工学や情報工学などのコースがあり、幅広い技術を学ぶことができます。
中でも情報科学部では、コンピュータサイエンスや情報システムなどの分野に特化した学びが提供されています。
また、
- 機械工学・システムデザイン学
- 電気電子物理工学
- 情報工学
- 応用化学
- 環境社会デザイン学
という5つの教育プログラムを設けているのも大きな特徴です。
エンジニアを目指せるおすすめの専門学校3選
エンジニアを目指すために専門学校に進む人は以下の3校がおすすめです。
- 日本電子専門学校
- 日本工学院
- HAL
専門学校は就職したあとにすぐに活躍できるカリキュラムを組んでいます。
各資格のサポートも充実しているので、即戦力を養ってくれるのが特徴です。
それぞれ特色があるので以下でひとつずつ詳しく見ていきましょう。
1.日本電子専門学校
日本電子専門学校は東京都新宿区にある専門学校です。
日本電子専門学校の特徴は「職業教育」と「キャリア教育」のバランスのとれたカリキュラム構成にあります。
- 職業教育・・・エンジニアに必要な知識やスキルを体系的に学ぶ
- キャリア教育・・・グループワークなどを通して社会に役に立つコミュケーション力を高める
(出典:日本電子専門学校)
上記のような特徴があります。
さらに日本電子専門学校は企業や団体などの連携を重視しており、企業に就職したら即戦力になれる人材を育てています。
そのため日本電子専門学校は各種の資格取得のためのサポート体制も充実しています。
2.日本工学院
日本工学院は「蒲田」「八王子」「北海道」の3つのキャンパスがある専門学校です。
日本工学院は6カレッジで専門的な34学科をもつ総合的な専門学校となります。
- クリエイターカレッジ
- デザインカレッジ
- ITカレッジ
- テクノロジーカレッジ
- ミュージックカレッジ
- スポーツ・医療カレッジ
(出典:日本工学院公式サイト)
上記のような6つのカレッジに別れており、それぞれ専門的に学んでいくことができます。
日本工学院は「専門力」「人間力」を身につけるための「教育設計図」という独自の教育システムを採用しています。
独自の教育システムをとおして社会に適応できる人材を育てているのが特徴です。
3.HAL
HAL専門学校は東京・名古屋・大阪に拠点がある専門学校です。
とくにゲームの分野に強く、日本ゲーム大賞2019アマチュア部門で大賞を受賞した実績もあります。
HAL専門学校は以下の分野を学ぶことができます。
- ゲーム分野
- CG・映像分野
- 音楽分野
- カーデザイン
- IT・Web分野
(出典:HAL公式サイト)
エンジニアを目指すならIT・Web分野がおすすめです。
エンジニアやクリエイターに必要な個性やセンスは最初からなくても心配ありません。
HALは独自のカリキュラムがあります。
- 創造性開発
- 自己開発
- 思考技術
HALは上記の科目を学ぶことで個性やセンスが磨かれていくのが特徴です。
4.KADOKAWAドワンゴ情報工科学院
KADOKAWAドワンゴ情報工科学院は、情報工学やデザイン、マンガ・アニメ制作など、幅広い分野で専門教育を行っています。
情報工学科ではプログラミングやネットワーク、セキュリティなどを学び、エンジニアとしてのスキルを磨くことができます。
またデザイン科やマンガ・アニメ制作科では、クリエイティブな技術や表現力を養うことができます。
学校独自のカリキュラムや施設を活用しながら、実践的な技術を身につけることができるのが特徴で、さらに業界との連携も密接であり卒業後の就職支援やキャリアサポートも充実しています。
5.東京情報クリエイター工学院専門学校
情報関連の専門教育を提供している学校で、コンピュータサイエンスや情報技術、デザイン、アニメーションなど、幅広い分野において実践的な学びを提供しています。
特に、プログラミングやデジタルデザイン、CG制作などの分野では、産業界との連携が強く、最新の技術やトレンドに即したカリキュラムが展開されています。
学校内には実習用のスタジオや最新のコンピュータ設備が整っているため、実践的なスキルを磨くことができます。
卒業後は、ゲーム開発会社やWeb制作会社、映像制作会社など、幅広い分野で活躍するエンジニアやクリエイターとしてのキャリアを築くことができるでしょう。
大学にこだわらないならプログラミングスクールを利用してエンジニアになる方法もある
エンジニアになるためにはスキルが必要なので、大学や専門学校への入学をしなければならないと思う方も多いでしょう。
ですが実際のところエンジニアの業務をやるうえでは大学や専門学校の卒業は、必ずしも絶対条件ではありません。
そのため、適切に効率よく、コストパフォーマンスのいい形の「プログラミングスクール」で学習をする方もいらっしゃいます。
スクールには以下のふたつのタイプがあります。
- 通学系のスクール
- オンラインスクール
スクールでプログラミングの学習をしたり、IT系の資格を取得すれば就職活動の際にアピールしたりすることができます。
自ら進んで積極的にプログラミングを習得した経験があれば、企業の面接担当者も注目してくれるでしょう。
そして結果的に高評価につながることが多いのです。
大学や専門学校に行かなくても熱意があればスクールに通ってエンジニアになることができるでしょう。
でもスクールって、結構高いイメージがありますよね…!
しかし、DMM WEBCAMPの学習コースなら月額 約15,000円~始められます!!
一生涯のスキルを学生の間に身に付けておけば、就活で引っ張りだこになること間違いなし!
まとめ:大学や専門学校の特徴を知って自分に合った方法でエンジニアを目指そう
エンジニアになる方法はいくつかの方法があります。
今回は大学と専門学校に分けて、それぞれメリットやデメリットがあることを紹介しました。
あなたの将来のためにどの方法が最適なのかをしっかり考えておきましょう。
- エンジニアになるためには大学・専門学校に通うのが一般的
- ほかの分野からでもスクール経由でエンジニアになることは可能
- 各学校のメリット・デメリットをしっかり確認する
IT系のエンジニアはこれらも不足することが予想されています。
国も積極的にIT人材の育成に力を入れているので、今後もますます活躍が期待される職種です。
今後、IT企業で働きたいのであれば、自分は大学向きなのか、あるいは専門学校向きなのかを見据えて進路を検討してみましょう。